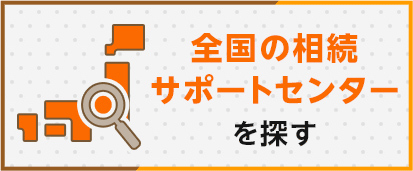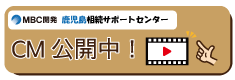はじめに
「遺言で長男に土地を引き継がせようとは思っている。そのうえで長男には今後も土地を守り続けてもらう事って可能?」
「今の法制度では、そこを強制することはできないです。ただお気持ちがあるのであれば、直接ご家族にご意向をお伝えしてみては?」
「ウーン…」
最近、このようなやり取りが増えたような気がします。非常に難しい問題ですし、この手の話に明快な答えがあるとは正直私も思っていません。そのうえで、今回はこの辺りの事情を私なりの視点で考察してみました。何かしらの一助になれば幸いです。
背景
背景にあるのは、親子間でのコミュニケーションがより困難になった現状があるのではと考えます。困難にする要因の一つが、世代間における価値観の断絶ではないかと考えます。
かつて日本の産業は米作りを中心とした農業が中心でした。この時代において、生きていくためには土地の確保所有こそが最優先事項でした。また、米作りは人手のかかる作業であるため、家族単位での連携も最重要項目でした。このような時代背景の中で、「長男が土地を引き継ぎ守り、家族は長男をサポートする」という考え方は、生き延びるために極めて合理的だったとも言えます。そして、この価値基準は日本文化に自然に根付いてきたように感じます。
しかし、戦後の大幅な技術革新は産業構造を大きく変化させました。産業の中心は農業から技術革新を背景としたサービス業・製造業に変化していきました。その中で個人は家に帰属するのではなく、会社へ帰属するようになりました。また、転勤などの移動も増加したことにより、生き延びるためには「フットワークの軽さ」も求められるようになりました。こうした時代背景の中で、「長男が土地を引き継ぎ守る」という考えに、必ずしも生き延びるための合理性があるようには感じられなくなってきたように思えます。
時代の急激な変化がもたらした代償として、一世代違うだけで生きてきた状況が全く別のものになってしまい、それが価値観の断絶を生み、世代間のコミュニケーションをより困難なものにしたのかもしれません。
そもそも、価値観に「良い」も「悪い」もありません。「正しい」も「間違っている」もありません。価値観は人それぞれ違って当然ですし、時代の合理性とともに変容していきます。実際私は現在50代前半ですが、最近新たに別の意味で「土地を守ること」の重要性を考えるようになりました。(この話は後述します。)
コミュニケーション不足がもたらす問題点
次に、コミュニケーション不足がもたらす弊害について、「親族間」「社会活動」の観点ら考察したいと思います。
親族間における弊害
「相続財産については、家族で話し合って決めればいい。遺言は書かない。自分たちも特に遺言は無かったが、問題はなかった。家族もそうしてくれるはず」ご家族を信じる気持ちは素晴らしいと思いますが、コミュニケーション不足の中で遺言のない相続はかなり厳しいと思います。
遺言がない場合、相続人全員の承認がなければ相続財産は共有状態が継続し続けます。相続人の中に一人でも頑なに主張を曲げない人物がいた場合、他の相続人は「(長期化当たり前の)法廷闘争」か「相続放棄」の二択を迫られます。長引く不況を背景に、兄弟姉妹といえども経済状況も踏まえ生きている状況は様々です。この状況下で「法廷闘争」か「相続放棄」の選択は人生に係る大きな負担となります。
また現在不動産経営は、資材高騰や人口減少を背景に厳しさを増しているという現状があります。相続人の中に不動産を引き継ぐ意向のある人物がいた場合でも、いきなり不動産を相続してすぐに経営ができるわけではありません。親族間の連携が取れていないと、守れた不動産も守れない結果になりかねません。
社会活動における弊害
不動産というのは、個人の資産であると同時に社会においては、生活の基盤そのものです。我々が暮らす街は、土地の上に存在しています。
数年前から、日本でも「空き家問題」が取り沙汰されています。様々な事情はあると思いますが、親族間の話し合いで回避できるケースもあると思います。このまま空き家が増え続けると、都市機能そのものを圧迫しかねません。治安の低下やインフラ整備の遅れは、我々一人一人の暮らしに直結する問題です。
また、近年では投資ではなく、投機目的での不動産の売買が増加しているように感じます。将来の街の発展を前提とした「不動産投資」ではなく、地域の風土や生活を無視し目先の利益のみを追求する「投機活動」は、地域経済の混乱を招きかねません。
「不動産を守る。街を守る。暮らしを守る。」ことの重要性は日に日に増しているように感じます。
本来、こういう活動は行政に期待したいところではあります。行政も決して動いてないわけではありませんが、やはり限界もあります。個人でできることにも限界はありますが、我々一人一人が自身の問題としてとらえ、できることは自分たちで対応するという意識を持つことが重要と考えます。
まずは、親族間で将来の不動産運用について話し合うというのも取り組みの一つなのかもしれません。
コミュニケーションをとることのメリット
親族間で相続の方向性が決まっていると、相続税の面でも積極的な節税を行う事ができます。逆に方向性が定まっていない状態では、節税の話はできません。下手に対策を打つ、そのことが将来の相続争いの要因になりかねません。
例えば、お孫さんを養子にするという節税の方法が有ります。相続人の数が増えることにより、相続税の基礎控除額が600万円増加します。また詳細は割愛しますが、相続税の計算構造上、相続人の数が増える事で税率そのものを低くする効果が期待できます。ケースによっては、1,000万円単位の節税も可能です。しかし、相続人が増えると「法定相続分」や「遺留分」にも影響が出ます。相続人間のコミュニケーションがない状態で安易に養子を増やすと、将来の相続トラブルに発展しかねません。
(※孫を養子にすることが相続税の不当減少と認められる場合は、否認される可能性があるのでご注意ください)
また、上述の通り現在不動産経営を取り巻く環境は、物価高騰や人口減少を背景に厳しさを増しています。事前に相続人のお気持ちを把握することで、より機動的に対策を講ずる機会も増えます。運用に自信が持てないのであれば、最近では「不動産信託会社」に運用を委託するといった選択肢もあります。
先の見えにくい時代だからこそ、「まずはご家族間で話し合ってみる事」の重要性は増していると感じます。
お互いの立場を尊重したうえでの歩み寄り
相続の話し合いで大前提は「相続財産の整理」です。本人は分かっていても、相続人には財産内容がわからないでは、話し合いの土俵に立てません。
次に「状況の整理」です。ご本人の立場や相続人の立場はそれぞれ違います。また、不動産を取り巻く状況も変化しています。そこを情報として共有しないと、話の前提がくずれ話し合いは迷走します。
そして、「心の整理」です。最終的にどのようにしたいかは、人それぞれです。ご本人の考えもあれば、相続人それぞれのお考えもあると思います。歩み寄れるところは歩み寄ればいいと思います。どうしても相容れないものがあれば、それはそれでよいと思います。相容れないのであれば、相容れないものとして、現実的な解決策を模索していくだけです。
不動産を取り巻く状況は、大変複雑です。ご家族だけで解決策を見つけ出すのは困難な部分も多々あると思います。その際は税理士や不動産のプロを有効にご活用ください。