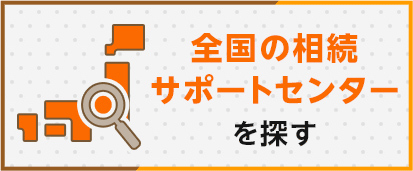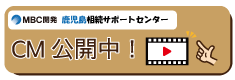多額の借金を負っている方が亡くなると、その相続人である家族は、亡くなった方にお金を貸していた方(債権者)から、借金の返済を求められます。
この場合、その相続人は、一定の期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことにより、借金を返済する責任を免れることができます。
しかし、次に記載するような「ある行為」をしてしまった場合は、相続を承認した(=借金などの一切を相続した)ものとみなされる可能性があります。
(1)相続財産を処分した場合
(2)相続放棄をした後、相続人であった人に背信的行為があった場合
順番に解説します。
まず、(1)の「相続財産を処分した場合」についてですが、たとえば、預金口座の解約、不動産の売却や家具・家電の廃棄などがこれに該当します。そして、一般的にこのような行為を「処分行為」といいます。
処分=捨てるというイメージがあるかもしれませんが、法律上の処分行為には、「財産の性質や形を変える行為」という意味があります。
たとえば、預金口座であれば、もともと銀行に対する預金債権という権利であったものが、解約により現金となりますので、これは、処分行為であるといえます。
このような処分行為を行ってしまうと、相続を承認したものとみなされるため、その相続人は、相続放棄の手続きを行うことができません。
相続放棄をした場合、その相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされますが、もし、処分行為を行ったことにより相続を承認したものとみなされた人の相続放棄を可能とした場合、矛盾することになるからです。
ここで1つ具体例について考えてみましょう。
亡くなった方が、生前に賃貸で部屋を借りていたとします。
部屋の所有者である大家(賃貸人)は、唯一の相続人であるあなたに次のことを求めてきました。
①賃貸借契約の解除(解除に関する書類への署名捺印)
②部屋の明渡しに伴う遺品整理
③部屋のクリーニング費用
しかし、亡くなった方には数百万円の借金があったため、あなたは相続放棄を検討しています。
この場合は、どのようなことに気を付けるべきでしょうか。
まず、①についてですが、そもそも賃貸借契約を締結した場合は、賃借人(部屋を借りる人)には、賃借権という権利(部屋に住むことができる権利)が発生します。
そして、その相続人が賃貸人との間で賃貸借契約を解除した場合は、賃借権という財産を処分したこととなります。
よって、これは処分行為に該当しますので、あなたはこれに応じるべきではありません。
では、賃貸人としては、このようなケースではどうすべきでしょうか。
方法の1つとして「家賃の不払い(債務不履行)による一方的解除」が考えられます。
通常、賃貸借契約書には、「2ヶ月以上家賃の滞納があった場合、賃貸人は、支払いの催告をせずに(一方的に)契約を解除することができる。」といった特約が記載されています。
この特約に基づき、賃貸人から一方的に契約を解除できれば、賃借人の相続人が契約を解除したというわけではないので、処分行為の問題もありません。
次に、②についてですが、これはどうでしょうか。
まず、賃借人には、賃貸人に部屋を返す際に、部屋を元どおりにする義務があります。これを原状回復義務といいます。
あなたが相続放棄をした場合は、この原状回復義務も免れますので、遺品整理なども行う必要がありません。
むしろ、遺品を引き取ったり、捨てたりすることは処分行為となり得ます。
では、どのような遺品であっても引き取ったり、捨てたりすることはできないのでしょうか。
これを考えるうえで、基準となるのは「慣行」と「遺品の経済的価値」です。
たとえば、亡くなった方が生前身に着けていた衣類などを遺族が引き取る、いわゆる「形見分け」という行為は、昔から習わしとして当然に行われてきたものであり、たとえ、相続放棄を行ったとしても、これを否定することは相当ではありません。
よって、形見分けについては、基本的に処分行為とはなりません。
ただし、形見分けであっても、経済的価値のあるもの、たとえば高級腕時計などは、形見分けの範囲を超えたものと考えられ、原則どおり処分行為となります。
そして、③についてですが、相続放棄をする以上、これも借金と同様に支払う必要はありません。
次に、(2)の「相続放棄をした後、相続人であった人に背信的行為があった場合」についてですが、たとえば、亡くなった方の通帳を管理している相続人が、相続放棄の手続き完了後に、この通帳から預金を引き出し、自分が欲しいものを買ったりするケースがこれに該当します。
相続放棄をした「元相続人」には、亡くなった方の財産を処分する権利はありませんので、これを処分することは、他人の財産を処分することと同じです。
よって、このようなことを防ぐために、背信的行為があった場合、「元相続人」は、相続を承認したものとみなされることとなります。
最後に、裁判所は、「処分行為があったこと」や「背信的行為があったこと」は、当事者から申告がない限り、基本的に、これを知ることはありません。
つまり、これらの事実があるにもかかわらず、「手続き上」は、相続放棄が認められることがあり得ます。
この場合、相続放棄の有効性はどのようになるのでしょうか。
結論から言いますと、後日、債権者などから訴訟を提起され、その裁判において、相続放棄が無効と扱われる可能性があります。
たとえば、ある債権者が、処分行為を行った「元相続人」を訴え、その裁判で、相続放棄の無効を主張し、借金の支払いを求めたとします。
そこで、裁判所が、この主張を正当なものと判断した場合、相続放棄は無効となり、「元相続人」は借金を支払わなければなりません。
このように、相続放棄には、気を付けるべきことが多々あります。
相続放棄を検討されている場合は、まずは、何にも手を付けないこと、そして、「安心して相続を放棄するため」にも、なるべく早い段階で、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが非常に重要となります。