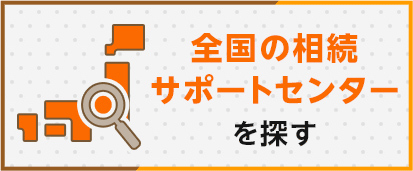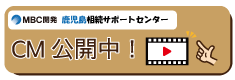年末が近付いてきたこの時期になると、私たちがお客様からいただくご相談の中で急増するものがあります。「今年の生前贈与、まだ間に合う?」という確認や、「贈与のルールが変わってからしばらく経つけど、結局我が家はどうするのが正解なの?」というお悩みです。
これまで多くの方が、年末の恒例行事のように行ってきたお子様やお孫様への資金移動。いわゆる「暦年贈与」と呼ばれる、年間110万円の非課税枠を活用した対策ですが、今は以前とは事情が異なります。ご存じの通り、昨年(2024年)より相続税と贈与税に関するルールが大きく変わり、その新制度も2年目の年末を迎えようとしているからです。
本日は、年末というタイミングだからこそ絶対に押さえておきたい「手続きの期限」と、新ルール2年目の今だからこそ考えたい「賢い贈与の戦略」について、要点を絞ってお話しします。
贈与の手続きの期限
まず、最も基本的でありながら、意外と多くの方が足元をすくわれてしまう「日付」の問題です。贈与税の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までです。そのため、今年の基礎控除枠である110万円を使い切るためには、12月31日までに贈与を完了させなければなりません。ここで注意が必要なのは、「12月31日に銀行で手続きをしたから大丈夫」とは限らないという点です。贈与の実績として認められるためには、相手の口座に着金したという事実が必要です。もし、銀行間の処理の関係で着金が年明けになってしまったら、その贈与は「来年分」として扱われる可能性があります。そうなると、今年は非課税枠を使えず、来年はその枠を倍使ってしまい贈与税が発生する、といった事態にもなりかねません。
「贈与契約書さえ年内の日付にしておけば大丈夫では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現金の贈与においては、当事者間の取り決めである「契約書の日付」よりも、客観的な事実である「受贈者がいつ管理・支配できるようになったか(=入金日)」が優先されるのが実務上の原則です。たとえ契約書の日付が年内であっても、着金が年明けになれば、それは「年明けの贈与」として扱われてしまうリスクがあります。やはり年内の着金が必須だと考えておくべきでしょう。銀行が混雑する年末ギリギリの振込みは避け、遅くともクリスマス頃までには手続きを完了させることを強くお勧めします。
税制改正の影響と賢い贈与戦略
次に、改めて「税制改正」の影響について整理しましょう。
長年親しまれてきた「暦年贈与」ですが、今回の改正により、相続税対策としての効力にメスが入りました。これまで、贈与者が亡くなった場合、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算するルールがありましたが、これが「7年」に順次延長されることになったのです。亡くなる直前の駆け込み的な対策が、以前より厳しくなったと言えます。
しかし、国は抜け道を塞ぐ一方で、次世代への資産移転を促すための「新しい選択肢」を用意してくれました。それが、リニューアルされた「相続時精算課税制度」です。従来は使い勝手が悪いと敬遠されがちな制度でしたが、改正により、暦年贈与と同じような「年間110万円の基礎控除」が新設されました。
この新制度の最大のメリットは、年間110万円までの贈与であれば申告不要であることに加え、その部分については、将来、贈与者に相続が発生した際も「持ち戻し計算の対象外」となる点です。
ただし、一つ注意点があります。相続時精算課税制度を初めて利用するときに限り、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならないという点です。この「最初の届出」を忘れると、暦年贈与を利用したと認定されてしまいますので、くれぐれもご注意ください。
この手続きさえ済ませれば、たとえ贈与の直後に贈与者の相続が発生しても、その110万円は相続財産に持ち戻す必要がありません。高齢の方や健康状態に不安のある方にとっては、従来の暦年贈与よりも圧倒的に有利で確実な制度へと生まれ変わっています。
改正から1年以上が経過しましたが、まだ「様子見」をして、従来の暦年贈与を漫然と続けている方も少なくありません。しかし、現在、暦年贈与を続けている皆様の多くは、この「新制度への切り替え」を検討すべき段階に来ています。
一方で、従来の暦年贈与にも勝ち筋はあります。それは「孫への贈与」です。相続開始直前7年分の贈与財産の持ち戻しルールは、基本的に「相続人(子など)」が対象であり、孫への贈与は原則として対象外だからです。
子には「新しい相続時精算課税制度」を使って確実に資産を渡し、孫には従来の「暦年贈与」を使う。こうした「使い分け」がこれからの主流です。一律に考えるのではなく、相手に合わせて最適な制度を選ぶことが求められる時代になったと言えるでしょう。
忘れてはならない「証拠作り」
最後に、どのような形であれ、贈与を行う際に忘れてはならないのが「証拠作り」です。ご家族間であっても、その都度「贈与契約書」を作成しておくことが、税務調査に対する最強の防衛策となります。また、現金手渡しではなく銀行振込を利用し、双方の通帳に記録を残すことも徹底してください。
年内に実行すべき三つのこと
これから年末に行っていただきたいことは三つです。一つ目は、今後の贈与の方針を決めること。そのためには、ご自身の年齢や資産規模、家族構成などに合わせて、「今年分から(あるいは来年から)制度を切り替えるべきか?」を専門家に一度シミュレーションしてもらうことをお勧めします。二つ目は、今年分の贈与手続きを早急に済ませること。そして三つ目は、契約書などの形式を整備することです。
あなたに合った最適な贈与プランをご提案します
制度が複雑になり、最適解を見つけるのが難しくなりました。しかし、ルールを正しく理解すれば、以前よりも安全に資産を承継できる道は開かれています。
ご家族が集まる年末年始は、将来について話し合う絶好の機会です。「我が家はどうするのが一番いいのだろう?」と迷われることがあれば、ぜひ私どもにお声掛けください。相続・贈与税に強い提携の税理士とともに、現状に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
▼今回のテーマに関連した過去の記事も、あわせてご覧ください。
- 贈与税制の改正を踏まえて令和6年以後の贈与をどうする? https://www.e-souzok.com/report/archives/666
- 【特別号】令和5年度税制改正大綱速報! ~贈与税の制度が大きく変わります https://www.e-souzok.com/report/archives/615